社内SEとして働き始めると、想像以上に「調整力」や「社内理解力」が求められます。
ITスキルよりも、“社内の人を巻き込む力”がカギになることも多いです。
ここでは、社内SE1年目が特につまずきやすいポイントと、実際に使える解決策を紹介します。
1. 何から手をつけていいかわからない
原因
社内SEの仕事は「システム運用」「トラブル対応」「ベンダー調整」「PC設定」など多岐にわたります。
マニュアルが整備されていない会社も多く、最初は全体像がつかめず混乱しがちです。
解決策
・1ヶ月目は“全体の流れ”を観察する期間にする。
社内の業務フローを図にまとめておくと、後で理解が一気に進みます。
システムを理解する前に社内業務を理解する方が大切です。
・担当範囲を明確にする。
上司や前任者に「どこまでが自分の範囲ですか?」と確認しておく。
・業務日誌をつける。
上司から義務付けられるかもしれませんが、日々の作業を記録することで、徐々に業務のパターンが見えてきます。
2. 社内からの問い合わせ対応に追われる
原因
「パソコンが動かない」「印刷できない」など、ヘルプデスク的な問い合わせが多く、
本来の改善業務に手が回らない状態に陥りがちです。
解決策
・対応履歴を残す。
Excelなどで「問い合わせ内容」と「対応結果」を残しておくと、同じ質問に素早く答えられます。
・よくある質問を共有する。
社内ポータルや掲示板にFAQをまとめて、同じ問い合わせを減らしましょう。
マニュアルを作成して配布することも有効です。
・「今すぐ対応」か「後で対応」かを分類。
緊急度を整理して優先順位を決めることで、精神的にも落ち着いて対応できます。
判断が難しい場合は上司に相談しましょう。
3. ベンダーとのやり取りが難しい
原因
技術的な専門用語が飛び交い、何をどう依頼すればよいのか分からないまま話が進むことがあります。
解決策
・「目的」と「要望」を明確に伝える。
「このシステムで何を実現したいか」を具体的に伝えると、ベンダーも正確に提案してくれます。
・打合せ内容をメモに残す。
後で上司や関係者に説明する際にも役立ちます。
・わからない言葉はその場で聞く。
「それはどういう意味ですか?」と率直に聞くことで理解が深まり、信頼も得られます。
これはベンダーだけでなく、社内業務を理解する際にも重要なことです。
4. 社内から「遅い」「わかりにくい」と言われる
原因
ITリテラシーの差が大きく、「相手に伝わる説明」ができないと不満が出やすいです。
解決策
・専門用語を避けて説明する。
「サーバーがダウンした」ではなく、「共有フォルダを置いているパソコンが止まった」と言い換える。
・対応の見通しを伝える。
「○時までに復旧予定です」と伝えることで、不安を減らせます。
復旧の見通しが立たない場合、30分~1時間ごとに社内ポータルや掲示板に報告することで、
「対応してくれている」という安心感を社内に与えることができます。
・マニュアルを簡潔に作る。
図やスクリーンショットを多用すると、誰でも理解しやすくなります。
5. 成果が見えにくく、モチベーションが下がる
原因
社内SEは「トラブルが起きないのが当たり前」になりやすく、努力が評価されにくいポジションです。
解決策
・「改善前→改善後」を数字で見せる。
例:「PC設定時間を30分短縮」「月○件の問い合わせ削減」など。
・社内報やミーティングで成果を共有。
他部署に「裏方の努力」を知ってもらうことが大切です。
・自分のスキルアップを可視化。
資格取得や勉強会参加など、成長を自分でも感じられるようにします。
まとめ:最初の1年は「信頼構築」がすべて
社内SEは、技術よりも「人との関係性」で仕事がスムーズに回る職種です。
最初の1年は
「すぐに解決できる人」よりも、「誠実に対応してくれる人」
と思ってもらえることを目標にしましょう。
信頼が積み上がれば、改善提案も通りやすくなり、あなたの影響力は確実に広がっていきます。
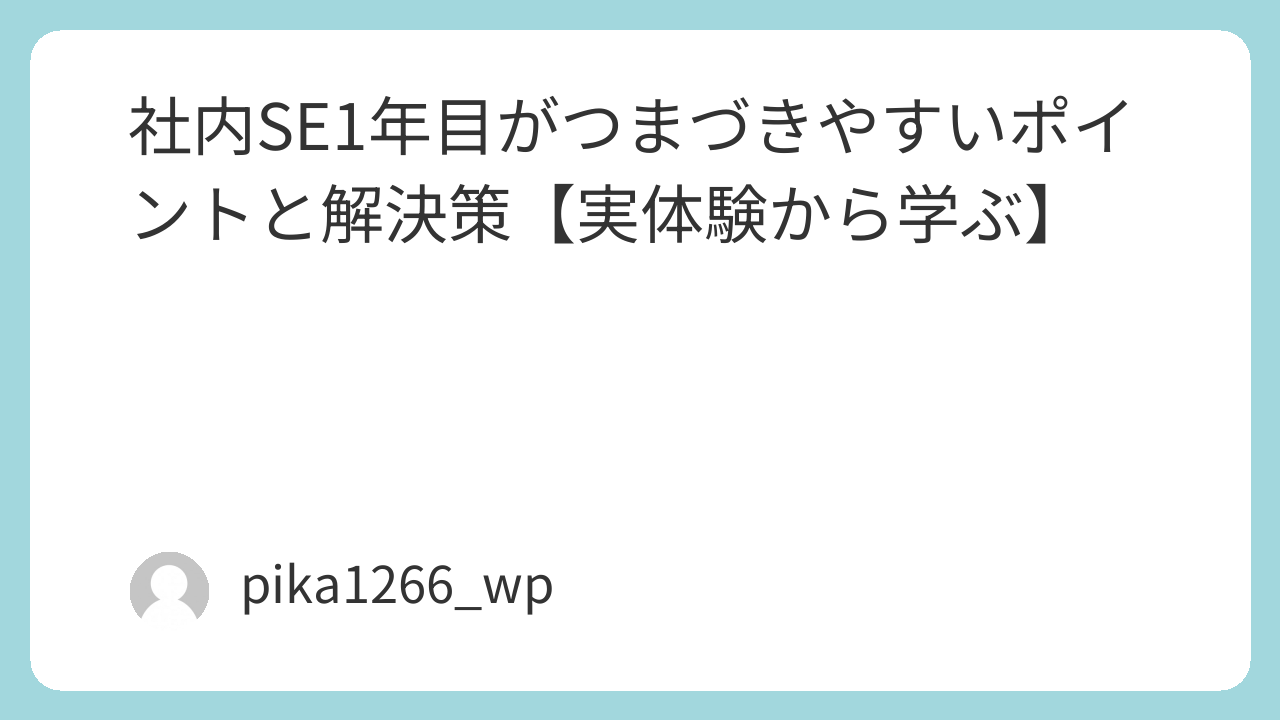
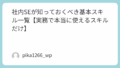
コメント